
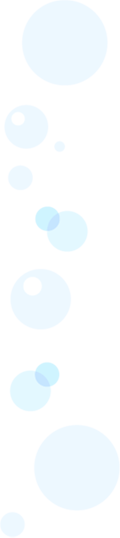
| カテゴリー1事業報告タイトル です |
|---|
| カテゴリー1会報タイトルです | |
|---|
会員博物館の実務に携わる職員が交流し、来館者の効果的な集客策を考案したり、館に従事する職員が学芸活動について様々なスキルを習得するために実施しています。
| 実施日 | 令和4年12月8日(木)、9日(金)の2日間 |
|---|---|
| 実施場所 | 石巻市 |
| 実施内容 | 1日目:みやぎ東日本大震災津波伝承館 石巻市震災遺構門脇小学校、 意見交換会 2日目: 石巻市博物館他 石ノ森萬画館 旧観慶丸商店 |
正会員博物館に対する理解の増進、発展の活性化に大きく寄与するイベントや企画展等の開催に対する正会員(正会員と協同でイベントや企画展等を行なう特別会員も対象)の活動を支援する助成制度です。
| 申請会員名 | 横浜みなと博物館 |
|---|---|
| 活動名 | 横浜みなと博物館リニューアルオープン記念展 ベストセレクション 世界の客船ポスター |
| 実活動内容 |
目的:客船ポスターの鑑賞を通じて、定期航路客船が20世紀半ばまで国際旅客輸送の主役であったことや、横浜港にも様々な国の客船が入港していたことを知ってもらう。
日時:イベント開催期間:2022年10月8日~12月4日 活動実施期間:2022年4月1日~2023年2月28日 入場者総数:7,325人 学芸員による展示解説:80人/ワークショップ「船のポスターを描こう」:32人 今回、みなとの博物館ネットワーク・フォーラムの助成を活用し、横浜みなと博物館では「横浜みなと博物館リニューアルオープン記念展 ベストセレクション 世界の客船ポスター」を開催しました。本展覧会では横浜みなと博物館が6月28日にリニューアルオープンしたことを記念し、当館の所蔵品から欧米と日本の海運会社が発行した1890年代から1960年代までの客船ポスターを計80点展示しました。入場者総数は7,325人で、横浜市内、神奈川県内はもちろん、他都道府県からも多くのお客様に御来場いただきました。 また、本展覧会の関連行事としてワークショップ「船のポスターを描こう」を実施しました。船舶イラストレーターの中村辰美氏を講師としてお招きし、10代から70代までの参加者に定期航路客船のポスターを制作してもらいました。この他にも関連行事として、学芸員による展示解説やタイタニック日本人生存者の手記の特別展示を実施しました。 展覧会の記録として、展示資料のカラー図版を掲載した展示解説目録を発行しました。横浜市内外の博物館や図書館に寄贈した他、当館ミュージアムショップでも有償で頒布しました。 本展覧会や関連行事の実施を通じて、定期航路客船が20世紀半ばまで国際旅客輸送の主役であったことや、横浜港にも様々な国の客船が入港していたことを来館者に伝えることができました。 |
| 申請会員名 | 敦賀市立博物館 |
|---|---|
| 活動名 | 敦賀市立博物館建物(旧大和田銀行本店本館)解説映像制作 |
| 実活動内容 |
目的:国の重要文化財に指定されている博物館建物(旧大和田銀行本店本館)を来館者に気軽にかつ具体的に知ってもらうための解説映像を制作する。また、制作した映像は博物館地下の休憩スペースにて開館中常時流し、来館者の目に留まるようにする。映像の内容は、年代を問わない教育普及教材として、近代敦賀港の発展に貢献した二代目大和田荘七や大和田銀行への理解を促進し、敦賀市立博物館の活動に関心を持ってもらえる内容とする。
日時:令和3年8月10日(水)~常時公開 場所:敦賀市立博物館 映像趣旨及び内容 当館の建物である旧大和田銀行本店本館は国の重要文化財に指定されており、今年(2022年)で竣工から95周年を迎えます。 敦賀は古代より交通の要衝として栄え、明治時代以降は鉄道と船の結節点として、開港場にも指定されました。この近代敦賀の発展に大きく寄与したのが二代目大和田荘七です。荘七は敦賀港の開港運動に尽力したほか、朝鮮牛の輸入や、商工会議所の設置、敦賀港の二度にわたる修築工事への出資など様々な事業に参画しました。この二代目大和田荘七が建てたのが旧大和田銀行本店本館です。旧大和田銀行本店本館は地下1階から地上3階まであり、館内には北陸で最も古いといわれる国産エレベーターが設置されていました。映像では、近代敦賀の歴史と、近代敦賀の商業経済の発展に大きく寄与した二代目大和田荘七、そして、荘七が建てた大和田銀行本店本館について紹介しています。 成果 これまでも博物館の地下1階は休憩スペースとして開放していましたが、利用者が少なく、あまり利用されていませんでした。また、来館者が見て学習できる映像解説の不足も課題でした。今回、本映像を設置したことで、来館者の地下室利用を促進できたとともに、港と鉄道の町として栄えた近代敦賀と、その繁栄を支えた二代目大和田荘七に対する理解向上に繋げることができました。 |
| 申請会員名 | 鳥羽市立海の博物館 |
|---|---|
| 活動名 | 企画展「海のパズル展 ~海の生きものであそんじゃお~」 |
| 実活動内容 |
目的:日本における食・遊び・信仰など多方面での“海ばなれ”が進む現状に対し、パズルを楽しみながら幅広い年代の方が海に親しむとともに、漁業・信仰・環境・生きものの生態など海の産業や文化について総合的に学ぶ機会を提供する。
日時:【展示】2022年4月29日~2022年8月28日 【付帯事業】2022年5月3日・8月11日 各日10:00~11:30「海のペーパーパズルを作ろう」 13:00~14:30「タコの木製パズルを作ろう」 参加者:【展示観覧】9,927名 【付帯事業】20名 ・展示室内では海に関連した多様なパズル・だまし絵・隠し絵を壁面や机上に多数設置し、ケース外のパズルは実際に体験をすることができるようにしました。 ・パズルを触って楽しんでもらいながら、海への親近感を高めてもらうとともに、海に暮らす生きものや漁撈習俗、信仰など海の産業、生態系、文化について総合的に理解を深めてもらうことにつながりました。 ・単に遊んで楽しむだけではなく、例えば氷河やシロクマがデザインに入ったパズルでは温暖化による氷の減少と海面上昇、釣りがテーマのパズルでは過度な漁獲による資源量減少の危険性を解説し、海洋環境の保護と持続的な資源利用の重要性などについても学習する場とすることができました。 ・付帯事業では、アマビエのペーパーパズル作りと、タコツボに入るタコの木製パズル作り体験を実施しました。パズル作家であり、海洋生物の研究者でもある講師を迎え、アマビエ信仰やタコの生態など様々な解説を添えてもらうことによって、モノづくりを楽しみながら、海の生きものの面白さや伝統的な漁業文化などへの理解を深めてもらうことができました。 ・展示実施に当あたっては新規に4点のパズルを制作しました(テーマは海の汚染・漁師の信仰・海洋汚染)。これらは企画展にて展示するとともに、会期終了後は当館の常設展内にて関連するコーナーに設置しました。これにより、当事業の成果を継続的に活用し、幅広い年代の方が海の親しみ、環境や信仰、資源利用の歴史などについて理解を深めやすくなりました。またこれらのパズルは学芸員の出前事業等においてもアウトリーチ教材として活用する予定です。 |
| 申請会員名 | 西宮市貝類館 |
|---|---|
| 活動名 | 西宮市貝類館特別展「ダンゴムシの街」 |
| 実活動内容 |
目的:私たちの身近にいるダンゴムシ。実はヨーロッパ原産の動物で、植木鉢などに紛れて船で運ばれてきたものと考えられている。ダンゴムシの仲間はとても種類が多く、田んぼや池、海の中にもたくさんの種類が住んでおり、この特別展は身近なダンゴムシとその仲間たちを紹介する特別展となる。
今回の特別展示において、ポスター展示、標本等に加え、特別展示「ダンゴムシの街」の内容を来館者の方により詳しく知ってもらうために、動画による投映を行う。昨今、動画による表現が主流となっており、新たに画質、解像度の高い動画対応のカメラを使用し、より小さないきものの生態の臨場感を感じてもらうことができるようにしたい。 日時:【令和5年3/16(木)~3/31(金) 参加者:732名 チラシ・ポスターの作成やさくらFMにてスポットCMを放送する等の広報を行いました。広報により特別展期間中は732人の方に来館いただきました。ダンゴムシは子どもの人気が高かったこと、また春休み期間中もあり、親子連れが多く見られました。 展示では、拡大写真による「巨大ダンゴムシの表裏」を作成、パネルを使用して細部まで観察できるよう工夫を行いました。また、北九州市立自然史・歴史博物館よりダイオウグソクムシ、大阪市立自然史博物館よりオオグソクムシといった巨大な海のダンゴムシをお借りし展示も行いました。アンケートにて「よく見るダンゴムシがヨーロッパ原産で船で日本に来た種類だとは知らなかった」といったご意見もあり、満足いただける展示となったかと思います。 初めての来館者へも今回の特別展をきっかけに、今後も施設の活性化へつなげていきます。 |
| 申請会員名 | 琴平海洋博物館(海の科学館) |
|---|---|
| 活動名 | 体験型展示の操作パネル等作 (動くブリッジ、ラジコン船、可変ピッチプロペラ) |
| 実活動内容 |
目的:日本人・外国人入館者、日本人・外国人観光客向け
日時:2022年11月30日~ 場所:館内展示物周辺に設置 当博物館は金刀比羅宮の山麓にあり、参詣や観光で琴平町にいらしたお客様が多く訪れます。 また、今年に入って新型コロナウイルスの感染拡大防止のために行われていた入国制限が緩和され、徐々に外国人のお客様の数も戻りつつあります。 この度の助成金により体験型施設の展示品の説明文や操作案内等のパネル(日本語・英語)を作成することができ、よりわかりやすい展示となりました。 今後も展示資料の見学満足度を高めるとともに、入館促進に努めていきたいと思っております。 |